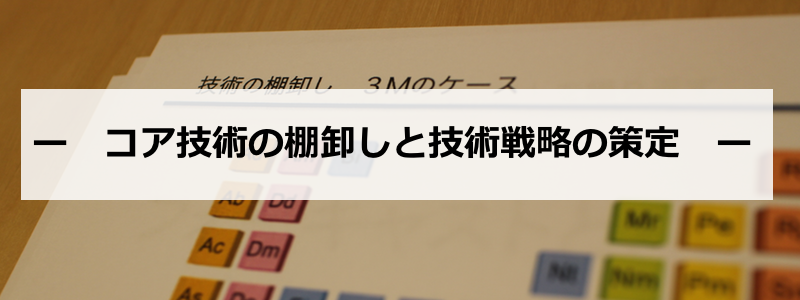技術棚卸しの目的は技術戦略策定
「技術の棚卸し」なのですが、どうしても「技術の棚卸しを実施してみたがうまくいかない」という感想をお聞きします。コレに対する私の答えは簡単で、「それはそうです、棚卸しは目的ではないのですから」です。「棚卸しのための棚卸し」では意味がないんですよね。
それこそ、技術の棚卸しの粒度や言い方など、細かい部分が問題になります。企画部門の依頼でデータを出して企画部門でまとめた、だけに終わりがちです。
目的が何なのか?によって技術の棚卸しの方法も内容も異なりますが、私の持論では、コア技術の棚卸しの目的は技術戦略の策定に尽きます。
技術戦略とは?
技術戦略とは、研究開発部門発の会社の成長戦略のことです。研究所には技術主導で会社を成長させる戦略が求められています。会社は、事業ポートフォリオを常に入れ替える必要があります。研究開発部門は、技術戦略とそれに伴う高収益な新商品・新事業を生み出せる仕組みにより会社の成長戦略に貢献するのです。
技術戦略には以下のものを含みます。
- 将来の成長産業・社会的要請・トレンド
- 成長産業・トレンドに必要な技術
- 当社技術との整合・不足技術
- 不足技術の獲得戦略
- 基盤技術ごとのロードマップ
技術の棚卸しとは?
技術の棚卸しの目的は、上記の通り、技術戦略の策定にあります。技術戦略の策定のためには、自社技術に対する正確な認識が必要です。
当然ながら、大分類ー中分類ー小分類で技術を一覧表にすることには留まりません。保有技術の組み合わせや見方を変えることにより、技術を適切な粒度で機能的に表現することが必要です。
この適切な粒度での機能的表現が、コア技術というべきものであり、このコア技術の認識により技術戦略を策定可能にするのです。
コンサルティングの概要
技術戦略の策定には、技術とビジネスの総合能力が問われます。長期テーマが欲しいか、短期テーマが欲しいかによりアプローチを変える必要がありますし、コア技術ベースのテーマ創出で得られるテーマはどのようなものかに関する理解が必要です。
このコンサルティングは、
①技術の棚卸しによって得られるものはなにか?
②どうすれば良いテーマが出るか?
③将来のコア技術の獲得計画を合理的な予想にするにはどうすればいい?
などの研究企画部門の疑問に対して解を提供しつつ、社内・研究開発部門の精鋭を巻き込んで実際にテーマ創出をするための活動です。
フォーキャストでなく、適宜バックキャストのアプローチを取り入れて要望に応じたテーマ創出の思考方法を実践していきます。フォーキャスト、バックキャストの具体的な方法・具体的な情報に触れて、思考方法の習得と同時に結果を生み出します。プロセスではなく、結果重視のテーマ創出活動です。
コンサルティングの特徴
特徴① 棚卸しと策定のプロセス(組織能力)に価値があることを理解する
技術の棚卸しと技術戦略の策定の成果は文書です。しかし、一度策定した戦略が将来に渡って100%正しいことなどありません。VUCAの時代、必要なのは戦略を随時修正・変更することであり、技術の棚卸しと技術戦略の文書に価値があるのではなく、策定に関与した技術者の経験や組織能力にこそ価値があると認識する必要があります。
VUCA(ブーカ)とは、Volatility(変動性・不安定さ)、Uncertainty(不確実性・不確定さ)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性・不明確さ)という4つのキーワードの頭文字から取った言葉で、現代の経営環境を取り巻く状況を表現するキーワードとして使われています。
特徴②本質的な技術の棚卸し
テーマ創出において、コア技術の棚卸しはエクセル作成ではありません。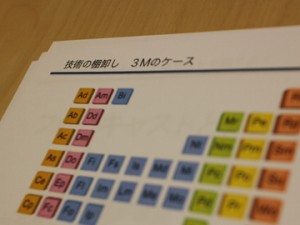
テーマ創出者が技術を理解することです。
理解することで類推能力や調査能力が飛躍的に高まり、テーマ創出力が向上します。
このプログラムでは、最初に理解の実践を行います。
特徴③技術戦略の策定
技術戦略は粒度に応じて、ロードマップにより表現することがあります。技術者はロードマップに沿ってテーマを創出します。
ロードマップには、自社のコア技術を中核としつつ、将来社会に必要な技術を獲得する計画や可能性を表現します。
ロードマップ策定には、関係する技術者が、将来社会に必要な技術が何なのかを検討するために情報収集することが重要であり、これを継続することが重要な組織能力であることを理解する必要があります。
進め方
ステップ1:技術の明確化
最初に対象の技術を明確にします。自社内にどのような技術があるのか、明確にする必要があります。一般的に技術は一覧化することにより可視化します。
技術の一覧化は、大企業では普通に実施されているものです。当社では、社内で実施することを強く推奨しています。どのような技術があるのかを、研究開発部門、生産部門、品質管理部門と部門ごと、あるいは製品ごとにに整理していきます。技術戦略策定の対象は、全社で実施する場合と技術毎に実施する場合があります。詳しくはお問い合わせください。
留意点:技術は代々継承されていく必要がありますが、この方法では一覧表(エクセル)を継承された新任担当者が社内技術を把握できないという致命的な欠点があります。ただし、何もしていない状態から進めるに際して一覧表の作成は必ず必要となります。
ステップ2:社会・技術トレンド情報の収集
将来の社会や技術トレンドの情報収集を行います。この情報収集の方法は産業により様々な方法があります。当社の提案する方法に沿って情報収集をし、将来の事業に必要な技術に関して、方向性のイメージを共有します。
- ①将来の社会はどのようなものか?
- ②将来社会における産業の位置づけはどのようなものか?
- ③どんな技術が必要になるのか?/可能になるのか?
を概括的に把握します。
留意点:プロジェクトメンバーでの技術理解をすすめることは極めて重要です。
ステップ3:事業動向・顧客課題の特定
ステップ2で大まかな方向性を踏まえて、このフェーズではより具体的に調査します。具体的には、事業毎に主要顧客を特定し、主要顧客が抱える課題を明確にします。このフェーズでは、営業情報や知財情報などを適切に併用して、顧客課題というニーズに近い言葉にしていきます。
主要論点
- ①事業にはどのような変化が予想されるのか?
- ②事業を維持するためにはどのような技術が必要か?
- ③顧客の課題はなにか?
- ④どのような新しい産業が出現しようとしているか?
ステップ4:技術の棚卸し・技術戦略の策定
ステップ1〜3を踏まえて、技術の棚卸しと技術戦略策定を実施します。ここまでの情報収集で、自社がどんな技術を持っているか、将来どんな技術が必要かのイメージが共有された状態です。
このフェーズは、イメージを具体的な文書にしていく作業です。目的に応じて、当社の提案するフォーマットに沿って、技術の棚卸しの成果及び技術戦略策定を文書化します。
ご準備頂きたいもの、進め方
ご準備頂きたいものは、参加する方々の時間とやる気です。斜に構えずに業務として取り組んでいただきたいと思います。
この活動は部門横断的な活動になるため、メンバー選定がキーポイントです。
対象 中堅社員以上(若手をまきこむことも推奨します)
人数 6名程度
期間 6ヶ月〜